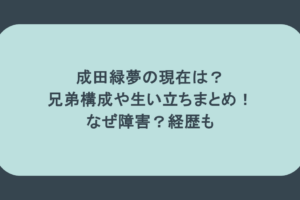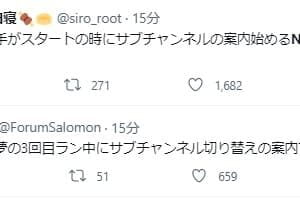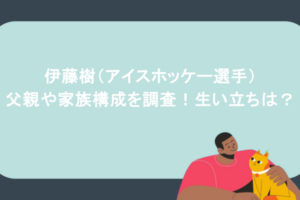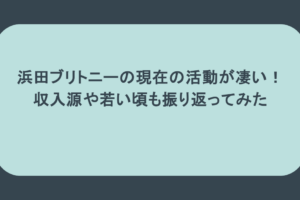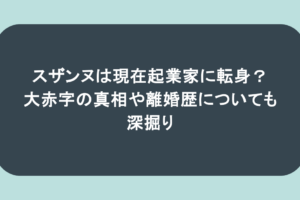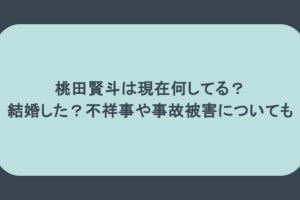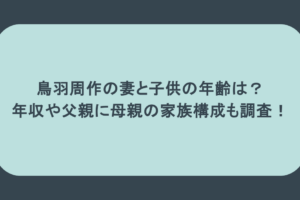パラリンピックでは数多くの競技が行われていますが、その詳細についてはあまり知られていないものも少なくありません。なかでも車いすバスケットボールは、そのスピード感とダイナミックな展開で観る者を魅了する人気競技です。競技ルールや魅力、そして意外と知らない車いすバスケットボールパラリンピック種目としての位置づけについて見ていきましょう。
この記事の目次
車いすバスケットボール(パラリンピック)とは
車いすバスケットボールは、下肢などに障がいを持つアスリートが車いすを使用して行うスポーツであり、パラリンピックの主要競技の一つです。国際的な人気を誇り、世界53の国と地域が国際車いすバスケットボール連盟(IWBF)に加盟しています。日本でも競技人口が約1,000人に達し、30のチームが日本車いすバスケットボール連盟に登録されています。
一般バスケットボールとの違い
車いすバスケットボールはコートサイズ、ボール、リングの高さなど基本的な設備は一般のバスケットボールと同じですが、いくつかの大きな違いがあります。
①「トラベリング」のルールが異なる
一般バスケットボールでは3歩以上歩くことが反則ですが、車いすバスケットボールではボールを持ったまま3回以上車いすをプッシュすることがトラベリングとなります。
②「ダブルドリブル」が認められる
一般バスケットボールで禁止される「ダブルドリブル」が車いすバスケットボールでは認められており、トラベリングに違反しない限り、ドリブルやボールの保持に回数制限はありません。
③「クラス分け」システム
車いすバスケットボール独特の「クラス分け」システムがあります。障がいの重さによって選手に1.0点から4.5点の点数が付与され、コート上の5選手の合計が14.0点を超えてはいけないというルールです。これにより、さまざまな障がい程度の選手が公平に競技できる環境が整えられています。
車いすバスケットボール:競技の魅力と特徴
車いすバスケットボールの魅力は、スピード感あふれるプレーと高度な技術にあります。選手たちは車いすを自在に操りながらボールハンドリングを行い、白熱した攻防を繰り広げます。一般のバスケットボールにはないダイナミックな車いす同士の接触や、時には転倒も伴う激しい展開は観る者を魅了してやみません。ルール上ジャンプは禁止されていますが、空中戦を制するために「ティルティング」という特殊技術を駆使します。片輪を上げて高さを出す高難度の技で、強靭な体幹が要求されます。
競技用車いすの特徴
競技用車いすは注目すべきポイントの一つです。タイヤがハの字に傾斜していることで、素早いターンと高い推進力を実現し、接触時には選手を保護するバンパーが機能します。また、選手ごとの体格や競技スタイルに合わせて、規定内でカスタマイズされることも多く、車いすそのものが競技の要となっています。
車いすバスケットボールの歴史
車いすバスケットボールの起源は第二次世界大戦後のアメリカにさかのぼります。1945年、戦争で負傷した退役軍人たちのリハビリテーションとして始まり、1948年には全米車いすバスケットボール協会が設立されました。日本では1960年代に普及が始まり、1961年の第一回大分身体障害者体育大会でデモンストレーションが行われました。1964年の東京パラリンピックを機に全国的な広がりを見せ、今日まで発展を続けています。
パラリンピック種目について
パラリンピック自体は第二次世界大戦後の負傷兵士のリハビリテーションを目的としたアーチェリー大会が起源とされています。1960年のローマ大会が第1回パラリンピックとして認識されていますが、「パラリンピック」の名称が初めて使用されたのは1964年の東京大会でした。現代では22競技539種目が実施され、車いすバスケットボールはパラリンピックでも人気競技の一つです。パラリンピックには水泳や陸上競技のように障がいの程度でクラス分けされる競技、車いすバスケットボールのように多様な障がいレベルの選手が同じチームで戦う競技、さらにボッチャのようなパラリンピック独自の競技など、様々な形式があります。
最後に
車いすバスケットボールは、障がいを抱えるアスリートが高い技術と戦略、そして情熱を持って競い合う競技で、パラリンピックを象徴する種目のひとつです。障がい者スポーツを知ることで、障がいを持つ方々が社会で果たしている役割や可能性を再認識する良い機会になります。車いすバスケットボールをはじめとする競技は、障がいに向き合い挑戦し続けるアスリートたちの姿を通じて、スポーツそのものの魅力を私たちに教えてくれます。次回のパラリンピック観戦では、競技の背景や特徴を知り、新しい視点で楽しむ機会にしてみてはいかがでしょうか。


の年収は?生い立ちや結婚してるかも調査-150x150.jpg)